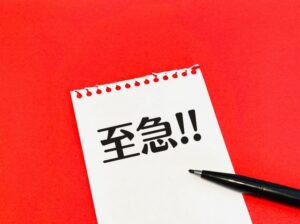二世帯住宅での車庫証明:申請時の注意点と必要な追加書類を徹底解説
二世帯住宅にお住まいで、新しく車を購入される方、または住所変更で車庫証明が必要になった方は、「書類作成が複雑になるのでは?」と不安に感じるかもしれません。
二世帯住宅の場合、敷地は一つでも、誰が、どのように、どこを使用するかによって、車庫証明に必要な書類が変わってきます。
本記事では、二世帯住宅特有の車庫証明申請時の注意点と、スムーズな申請のために必要な追加書類について、行政書士が詳しく解説します。
1. 二世帯住宅の車庫証明で最も重要なポイント
二世帯住宅での車庫証明申請で、警察が重視するのは、「申請者が車を保管する場所を、法的に正しく使用できる立場にあるか」という点です。
二世帯住宅は「土地の所有者」と「車の使用者」の関係が複雑になりやすいため、以下のどちらのケースに該当するかを明確にする必要があります。
A. 敷地の所有者が、申請者本人または配偶者である場合
このケースは、自分が所有する土地に、住民票を置いて住んでいる場合などが該当します。
B. 敷地の所有者が、申請者本人や配偶者以外である場合
親族(親や兄弟)が所有者である敷地の一部を、申請者が利用する場合です。
2. 申請時の注意点:二世帯住宅特有の落とし穴
注意点1:使用承諾書が必要になる境界線
車庫証明の申請書類の一つに、「保管場所使用権原書」があります。これは以下の2種類に分かれます。
| 権原書の種類 | 申請者が保管場所を所有している場合 | 申請者が保管場所を借りている場合 |
| 書類名 | 自認書 (自分で所有していることを証明) | 使用承諾証明書 (所有者から承諾を得ていることを証明) |
二世帯住宅では、以下のケースで「使用承諾証明書」が必要になります。
- 土地の名義が親になっており、子が車庫証明を申請する場合。
- 土地が夫婦の共有名義だが、片方の名義人が車庫証明を申請する場合。
親族間であっても、土地の所有者と申請者の名前が完全に一致しない場合は、「使用承諾証明書」を提出する必要があります。
注意点2:共有駐車場の場合の配置図の書き方
二世帯で駐車場を共有している場合(例:スペースが3台分ある)、配置図には申請者が使用する保管場所を明確に示す必要があります。
- 配置図上のどのスペースを、どの車が使用するのかを詳細に記載し、他の車と区別できるようにします。
- 例えば「申請車両は、南側から2番目のスペースを使用」といった具体的な情報を書き込みましょう。
注意点3:住民票の住所との整合性
車庫証明の申請書に記載する「使用の本拠の位置」(申請者の住所)は、原則として住民票の住所と一致していなければなりません。
二世帯住宅で住民票上の住所が1つであっても、実際に住居として使用している場所を正確に記載してください。
3. スムーズな申請に「必要な追加書類」
二世帯住宅での申請をスムーズにするために、上記の「使用承諾証明書」以外にも、状況に応じて追加で求められる可能性がある書類があります。
1. 保管場所使用承諾証明書(必須となるケースが多い)
- 誰に書いてもらうか?:土地の所有者本人(親や共有名義の配偶者など)
- 注意点:承諾証明書に押す印鑑は、所有者の実印でなくても構いませんが、書類が間違っていないか確認してもらうことが重要です。
2. 土地・建物の登記簿謄本(コピーで可)
所有者との関係性を確認するため、警察署によっては提出を求められることがあります。特に、二世帯住宅の権利関係が複雑な場合に有効です。
3. 住民票の写し(住所の確認のため)
親族間の申請の場合、親族関係や住所の整合性を証明するために使用されます。
4. まとめ:二世帯住宅での車庫証明は行政書士へ
二世帯住宅の場合、「親族間だから大丈夫だろう」と自己判断してしまうと、書類の不備で警察署への再提出や手続きの遅延が発生しやすいのが実情です。
特に「使用承諾証明書」の取得は、所有者(親御さんなど)に印鑑を押してもらう手間も発生します。
行政書士に依頼する3つのメリット
- 必要な書類を正確に判断:お客様の家族構成や土地の名義を確認し、必要な書類を過不足なくご案内します。
- 煩雑な書類作成を代行:「所在図・配置図」や「申請書」の作成・記入を全て代行します。
- 警察署とのやり取りを全て代行:平日昼間の警察署への訪問、書類の提出、交付後の受け取りまで、お客様の手を一切煩わせません。
二世帯住宅の車庫証明でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。最短での車庫証明取得をサポートいたします。
「自動車のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
郵送・連絡先この記事を書いた人

-
自動車専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
迅速・丁寧・確実な許認可サポート
最新の投稿
- 2026年1月3日車庫証明学生の一人暮らし。親名義の車を持っていく時の「使用の本拠」の書き方は?車庫証明のコツを解説
- 2026年1月2日自動車登録単身赴任中のパパ。車のナンバーは住民票の場所じゃないとダメ?行政書士が徹底解説!
- 2025年12月24日自動車登録ディーラーに頼むと高い?名義変更代行費用の内訳と賢い節約術
- 2025年12月24日自動車登録車検証の「使用者」と「所有者」を分けるメリット・デメリットとは?